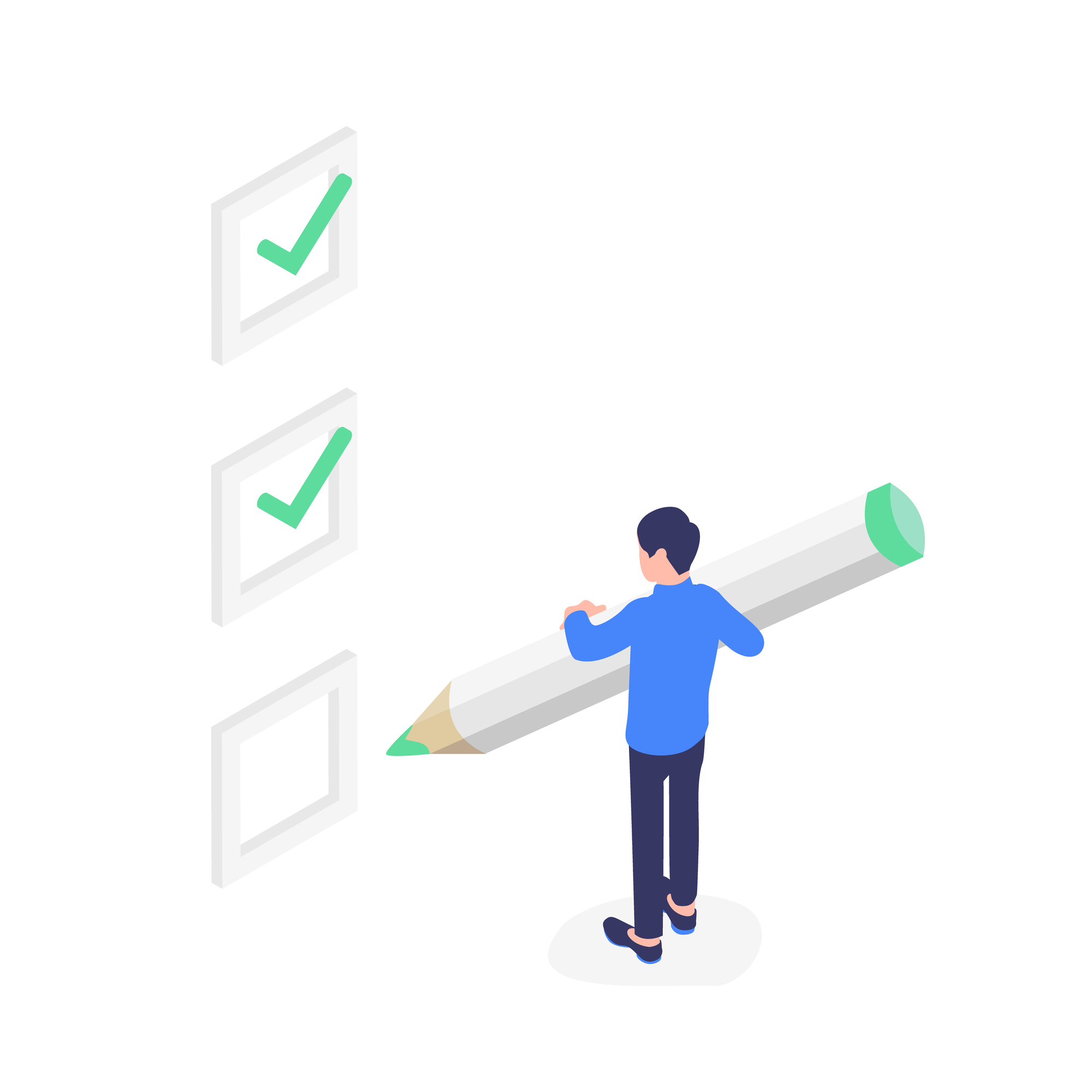厚生労働省は2025年7月7日、有識者による「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」(座長:今野浩一郎・学習院大学名誉教授)の報告書を公表しました。
報告書では、人材開発政策の今後の基本的な方向性について、次の4つの柱に整理して示しています。
・労働市場におけるスキルや職務の「見える化」の促進
・個人のキャリア形成と能力開発支援の充実
・企業の人材開発への支援の強化
・人材育成機会の拡大と技能振興
現在の「第11次職業能力開発基本計画」(2021〜2025年度)の終了を控え、本報告書は、2026年度(令和8年度)から始まる次期計画の策定に向けた検討資料として位置付けられています。今後は、厚労省の労働政策審議会人材開発分科会において、本報告書の内容も踏まえた審議が行われる予定です。
■目指す社会像 キャリアは自律的に、育成は企業と社会とともに
報告書では、人材開発政策により実現を目指す社会の姿として、以下の3点を示しています。
・個人が、職業人生を通じて、技術の進展や産業構造の変化に応じてキャリアを自律的に形成し、スキルの向上と適職選択をはかること
・企業が、経営環境の変化に対応しながら人材開発に積極的に取り組み、生産性向上と人材投資の好循環を実現すること
・社会全体が、労働市場の仕組みを通じて、働く人が能力を発揮できる職業に就ける環境を整備すること
■人材開発政策の視点は、個別化・共同化・見える化の三本柱
報告書では、今後の人材開発政策を検討する際の視点として、次の3点を挙げています。
〇個別化 個人と企業に合わせた支援の必要性
キャリア形成には、労働市場や企業環境、自身の能力や志向を踏まえた上での設計が望まれるが、個人がそれを独力で行うのは難しい。報告書では、考える機会の提供や、状況に応じた「伴走型の支援」が必要であるとされています。
企業においても、好事例の共有や外部支援の情報を活用しながら、自社に合った計画づくりが求められます。
〇共同・共有化 企業を越えた連携による効率的育成
中小企業では、訓練計画の作成やOFF-JT(職場外研修)の実施に関する負担が大きく、人材育成の取り組みが停滞しやすい。報告書では、指導者や訓練設備、ノウハウを複数企業で共有する体制を整えることで、育成コストの低減や効率的な訓練の実施が可能になると指摘しています。
〇見える化 職業情報やスキル評価の整備
キャリア形成や人材採用・育成の基盤として、職業・作業(ジョブ・タスク)やスキル、処遇に関する情報を整理し、見える化する取り組みが求められています。
こうした「見える化」の施策の一例として、厚労省では「job tag(ジョブタグ)」と呼ばれる職業情報提供ツールを整備しており、ハローワークの求人や講座情報と連携した情報提供を進めています。
■実現に向けた課題 企業・個人・制度の三層で対応が必要に
報告書では、目指す社会像を実現するための主な課題として、以下の点を挙げています。
・企業・労働者による人材開発の促進
・労働供給制約と人材不足への対応
・自律的・主体的なキャリア形成の支援
・デジタル技術の進展への対応
これらの課題に共通しているのは、企業の人材投資や、労働者を取り巻く環境の変化への対応が不可欠であるという点です。報告書では、企業・個人・制度の三層がそれぞれの役割を果たしながら、連携して課題解決に取り組む必要があるとしています。
今回公表された報告書は、2026年度からの適用が予定される第12次職業能力開発基本計画の検討に向けた議論の材料とされています。今後は、労働政策審議会人材開発分科会での審議を経て活用される見込みです。
報告書の詳細は、厚生労働省のホームページで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59371.html